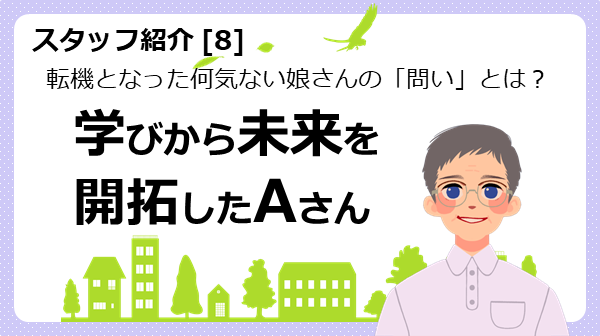
この連載は、あなたが一歩前へ踏み出す情報をちょうふサポステならではの要素を加えてお届けいたします!
こんにちは、ブログ担当のスタッフSです。3月に入り、桜の開花も待ち遠しい季節になりました🌸
さて今回は、ちょうふサポステの大先輩、穏やかで安心感あふれる存在のスタッフAさんをご紹介いたします!
【Aさんのプロフィール】
>娘さんの一言がキャリアの転機に
>好きな言葉は、ネガティブ・ケイパビリティ
>利用者さんに一言!
娘さんの一言がキャリアの転機に
――― Aさんの歩まれたこれまでの道のりを伺えますか?
Aさん:僕は昔、集団が苦手でした。そこから様々な方との出会いを経て、大学教員として研究でわかっていることを伝えるだけでなく、自分の足を使って新しいことを発見し、それを伝える役割というか使命というか、そういった不思議な巡りあわせを感じながら今に至っています。
娘がいるんですが、障がいがあるので作業所に通っていましてね。そのうちにもっと給与がもらえる仕事をと自然に彼女はそういう道に進み、介護のバックヤードの仕事で温かい同僚に囲まれて「今日は、誰々さんと誰々さんが待ってる!」と列挙して 気分よく出掛けていくんですよ。
そんなある日、仕事に向かう私に、「パパのことは、誰が待っているの?」と聞かれましてね。あれ?僕のこと、誰か待ってたかな?と一瞬ぎくりとして「そうだ、何々くんが……」とかしどろもどろで答えてしまったりして(笑)。
娘の「待ってる」というその言葉がね、なんか後からじわじわと来るわけですよ(笑)。
――― 何気ない娘さんの一言がボディーブローのように効いてこられたのですね……🤭
Aさん:そう、それまでは学生にテーマを渡して指導したり、引っ張っていくような関わりだったんですが、そこから徐々に関わり方に変化が生まれていったように思います。
研究室を希望する学生の中には、これがやりたいと言ってくる学生ばかりではなく、研究とは関係のないテーマに興味を持っていたり、何をやっていいかわからないと言う学生の方が圧倒的に多いんです。それで僕は、「なんでもいいよ。好きなことがあれば持っておいでよ」と。難しいことは分かっていましたがそうしてみたんです。
――― 通常とは異なるアプローチを選択されるのは勇気のいることと思いますが、悩んでいる学生さんからしてみたら、とても心強いんじゃないかと。
Aさん:そうなのかな。アプローチを変えるとね、学生自身が好きなテーマを持ち込む方が研究になることにも気づいたんです。特に未知の挑戦であればなおさら。学生から「先生だからこのテーマが研究になるか知っているでしょう?」 と聞かれても、知らないものは知らないのよね(笑)。「誰かやっているかもしれないから、調べてみれば?」と促すと、学生の方から一生懸命に調べて教えてくれるようになりました。
――― ご自身の変化と共に、受け身だった学生も主体的に変化して行かれたんですね。
Aさん:そこから「学び」と「研究」が、密接に結びついていることを実感するようになりました。最近ではAIに代表されるようなコンピューター学習が話題になっていますが、例えば、CPU(コンピューターの中央演算装置)自体に学習機能を持たせると面白いなと思い始めちゃったりなんかしちゃって😊
――― なんと!?(突然高次元なお話になり、こんな返しになってしまいすみません。。)
Aさん:CPUがソフトウェアを実行するときにソフトウェア自体を学習するような仕組みを持たせれば、人間とソフトウェアの関係性をより緊密に結びつけることができるんじゃないかと考えてみたんです。
インターネット・プロトコル(インターネット上の通信の手続き) 自体に学習の機能を持たせることで、その上で処理されるデータのパターン自体を研究させることができるんじゃないかと。
例えば、コンピュータ・ウイルスは迷惑な存在で、これまでにないようなウイルスが誕生すると防ぐ手立てもない。このコンピュータ・ウイルスを培養して振る舞いをインターネット・プロトコル自体に学習させることができれば、未知のウイルスに対しても発見できるような仕組みができるかもしれない。みたいな。
――― 現在ではAIの活用で未知の脅威にも対応可能に進化してきているウイルス対策ソフトですが、当初は元々あるウイルスの「型」でしかキャッチできなかったと聞いたことがあります。Aさんは、まさにその先陣を切って研究をされていたということでしょうか……!?😳
Aさん:そうなのかな😊
3.11の震災時には、被災した学生の友人が住んでいた家の浸水がひどくて、「津波がさかのぼる力を予測できないか?」と話してくれた学生がいました。また別の時には、バーで働いていた学生からカクテルをシェイクする際の「美味しくなる振り加減」についての話があり、それが津波の研究とつながって、活かせたこともありました。
――― 一見、何の繋がりもないような物事が結びついていく過程というは、ワクワクが止まりませんね!
Aさん:そうでしょう?^^
僕は論文がぜんぜん書けなくて。自分なんかダメだと苦しんだ経験がある分、学生が嬉々として論文を完成していく姿を見るのはとても嬉しい体験でした。
――― そんなAさんですが、現在では名誉教授になられて、色々な活動がある中でサポステの相談員としての 役割も担っていらっしゃるのですね。
Aさん:若者と関わる中で、自分よりも深い経験を持つ彼らから多くを学び、人生の先輩だなと感じています。娘の「誰が待ってる?」という一言をきっかけに、かつて集団が苦手で他者が居心地の悪い存在だった自分が、ここまで変わるなんて不思議なものでしょう。この年齢になってようやく自分が何者なのか、その手がかりを見つけられたばかりです(笑)。それもすべて、これまで出会い、関わってきた人たちのおかげです。その恩返しを僕はしていきたいな。

好きな言葉は、ネガティブ・ケイパビリティ
――― 好きな言葉(座右の銘など)教えていただけますか?
Aさん:「ネガティブ・ケイパビリティ」です。
困難な状況で明確な答えがすぐには見つからない、不可思議で対処できない事態を耐え抜く力を意味します。
――― 初めて目にする言葉という方も多いかもしれませんが、答えのない不確かさや曖昧さと共存する能力とも言われますよね。結論を急ぎがちな現代を生きる私たちだからこそ、難しいと感じる方も多いかもしれませんが。
Aさん:そうですね。簡単にできることではないからこそ、生まれた言葉なのかもしれません。わからないからこそ、一生懸命理解しようとする。その姿勢こそが大事なのかな。そのシグナルとして捉えています 。
――― 簡単にできないからこそ、意識するための言葉……。私自身もこの言葉はとても特別で大切にしている考え方だったので、改めて「ハッ」とさせられます。
Aさん:でも、こだわりすぎると深みにはまりすぎてしまうこともありますでしょう。わかりたいけど、わからない。それでも「できるといいな」と思いながら過ごす。そのモヤモヤする時間自体が、「不確かさとともに生きている」ということなのかもしれません。
――― その時はわからなくても、不確かさの中で答えが熟成され、5年、10年経ってようやくその意味が見えてくることもあるかもしれませんね😌

それでは最後に利用者さんに一言お願いします!
Aさん:僕は、ちょうふサポステのチームワークの良さを伝えたいな!
みなさん利用者中心に動いている。当たり前かもしれないけれど、お互いをリスペクトしている。
利用者はむしろ先生で、僕みたいななまっちょろい生き方ではなく現実をちゃんと認識されている存在。「一緒にいるよ。そばにいるから。学びという意味では、私たちも同じなんだよ」という気持ちなんです。だから、あなたの持っている力に気づいてほしいなあ。そんな風に思っている僕です。
今回、Aさんがさらりと語ってくださった一つひとつのエピソードからは、豊かな経験と深い学びが滲み出ているように感じられました。そして娘さんをはじめ、出会った方々へ「恩返しをしていきたい」というその言葉がとても印象的で、心温まる思いがしました。Aさん、貴重なお話をありがとうございました!
春の訪れとともに、新しいスタートを切りたいあなたへ。無理のないペースで新たな一歩を踏み出してみませんか?私たちが一緒にお手伝いできることがあるかもしません。お気軽にお問い合わせください(^^)/
・スタッフ紹介【Vol.7】 フラットな視点で魅力を放つIさんはこちらから↓↓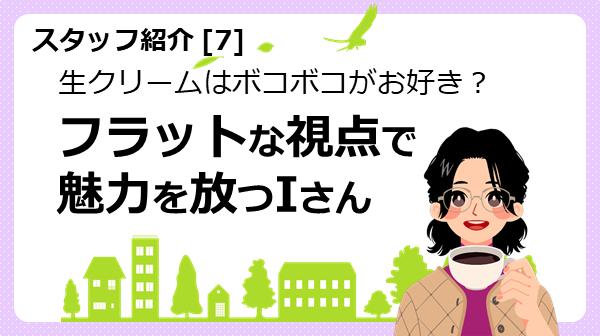
・スタッフ紹介一覧はこちらから↓↓
・過去のブログはこちらから
 はじめてのご相談・初回相談はこちら
はじめてのご相談・初回相談はこちら